

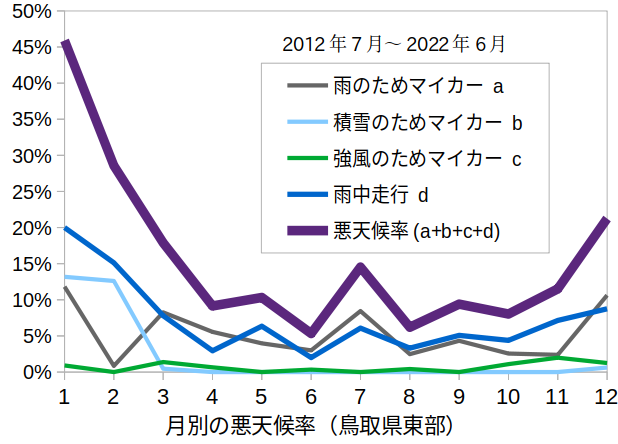


主な消耗品と交換費用
| 単価 | 交換距離(km) | 交換回数 | 総交換費用 | |
| ギアワイヤ | ¥1,700 | 4000 | 3 | ¥5,100 |
| ブレーキワイヤ | ¥1,700 | 4000 | 3 | ¥5,100 |
| シャフト | ¥2,400 | 4000 | 3 | ¥7,200 |
| タイヤ(前後) | ¥6,000 | 4000 | 3 | ¥18,000 |
| チューブ(前後) | ¥2,400 | 4000 | 3 | ¥7,200 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通勤経路 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||
| CEN 兵庫県香美町にて | ||||||||||||||||||||||||||||||
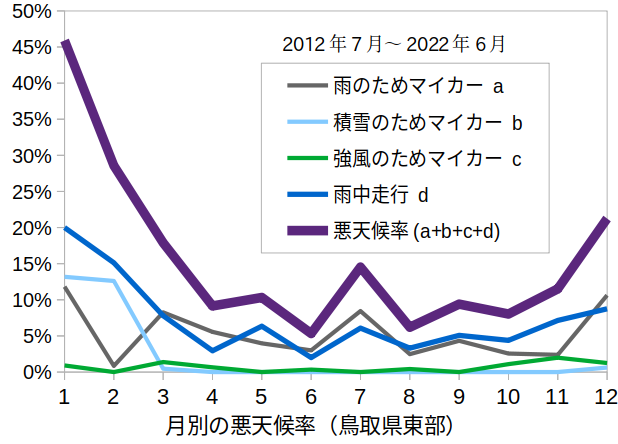
| ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCAPE 兵庫県新温泉町居組にて | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||
| PPECISION 砂丘サイクリングロードにて | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
主な消耗品と交換費用
|