読後感想 井関正久著「ルディ・ドュチュケと戦後ドイツ」(出版:共和国)
2024年5月28日 藤巻晴行
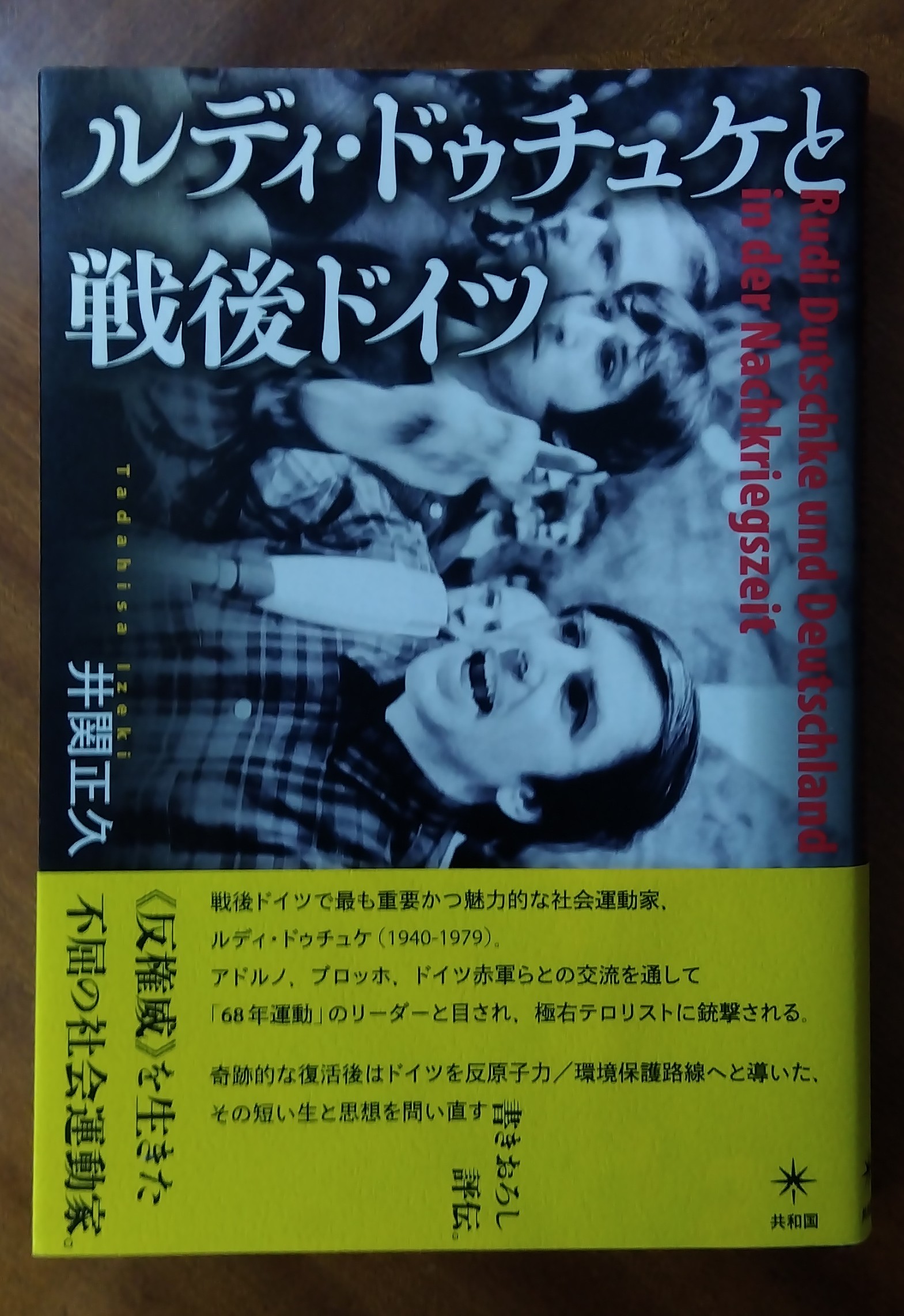 ルディ・ドュチュケは1940年東ドイツ生まれで軍入隊を拒否して西ドイツに逃れ、そこで学生運動のリーダーとなり、運動が頂点に達した1968年に極右青年の銃弾を受け瀕死の重症を負うものの、再びオピニオンリーダーとして「議会外反対運動」を推し進め、"ジーンズにセーターの議員団"緑の党(Die Grürnen)の結成の立役者の一人となり、結党直前の1979年に後遺症で死去した左派活動家である。東独の偽りだらけの「社会主義」体制もソ連によるチェコスロバキア侵略もドイツ赤軍によるテロも強く批判した民主主義的社会主義者であった。本書は一人の魅力的な人物の短くも波乱万丈の生涯を軸に戦後ドイツの政治史をたどるもので、ドュチュケ自身が運動の個人化に困惑し神格化に批判的であったことを踏まえつつ、平板な通史解説より惹き込まれる秀逸な手法で戦後ドイツの政治状況を伝えている。
ルディ・ドュチュケは1940年東ドイツ生まれで軍入隊を拒否して西ドイツに逃れ、そこで学生運動のリーダーとなり、運動が頂点に達した1968年に極右青年の銃弾を受け瀕死の重症を負うものの、再びオピニオンリーダーとして「議会外反対運動」を推し進め、"ジーンズにセーターの議員団"緑の党(Die Grürnen)の結成の立役者の一人となり、結党直前の1979年に後遺症で死去した左派活動家である。東独の偽りだらけの「社会主義」体制もソ連によるチェコスロバキア侵略もドイツ赤軍によるテロも強く批判した民主主義的社会主義者であった。本書は一人の魅力的な人物の短くも波乱万丈の生涯を軸に戦後ドイツの政治史をたどるもので、ドュチュケ自身が運動の個人化に困惑し神格化に批判的であったことを踏まえつつ、平板な通史解説より惹き込まれる秀逸な手法で戦後ドイツの政治状況を伝えている。
ドイツは社会民主党(SPD)と自由民主党と緑の党のいわゆる信号機連合のもと原発を廃止し先進国トップクラスの再生可能エネルギー発電率を達成し、高水準の福祉を維持し、多くの難民を受け入れて手厚く保護しつつ健全財政を維持し、着実な経済成長を続け、ついに人口が1.5倍の日本のGDPを抜いた奇跡の国である。ドイツと同様にファシズムと敗戦を経験した後発先進工業国として、日本が学ぶべき点はなお多い。なぜ日本に緑の党が誕生し得なかったのか、なぜ日本では80年代以降、若者によるデモをはじめとする政治参加が稀なのか、かねてより関心があったため興味深く手に取った。
ドュチュケは東ドイツの教育を受けながら「社会主義」体制の欺瞞に気づき軍入隊を拒否する。まずここに驚く。教会が重要な役割を果たしたようであるが、いかにして民主主義的社会主義者としての思想的土台が育っていったのか、なお解明が求められる。イデオロギー統制、言論弾圧からの批判的精神の避難所、抵抗の拠点としての教会の役割は著者の「戦後ドイツの抗議運動 − 『成熟した市民社会」への模索」(2016)でも論じられているが、今なお政治学の重要なテーマであろう。今のロシアや中国にそのような場はあるだろうか。
亡命先の西ドイツで学生運動にのめり込み、たちまち指導的存在となる。当時、旧ナチ党員らが何知らぬ顔で社会の中枢を担っていた。彼らは今なお権力に無批判に迎合し弱者には権威をふりかざしファシズムを支えた「権威主義的人間」のままであり、彼らとたたかうことがナチの再来を防ぐために欠かせないとドュチュケらは考えていた。
66年にアメリカ人と結婚し、子供を授かるが、男女同権、性的役割分担の克服についても当時のドイツの左派活動家としては理解と受容が早かった。
67年、イスラエルが今に続く国連が認めない占領地を手にした第3次中東戦争に際しては、学生運動組織(SDS)におけるイスラエル非難の決議を阻止した(p88)。無条件のイスラエル支援というドイツが抱える宿痾をドュチュケも抱えていたことは興味深い。ドイツ人にはその宿痾を自覚し克服することを期待したい。一方で、60年代末に連帯を表明していたキューバやベトナムがアメリカの干渉戦争を打ち破った後、旧東欧諸国と同様の独裁体制を続け言論の自由をはじめとする人権を抑圧していたことに対する彼の反省の弁を聞きたかったものである。
68年の激しい学生運動の抗議対象の一つが非常事態法であったと記されている。改憲派から、しばしば過去にファシズムを経験したドイツも非常事態法を有しているから日本国憲法にも緊急事態条項の導入は当然である、との主張がなされるが、広範な国民合意の下での制定ではなかったこと、抗議活動により独裁化への一定の歯止めがなされたことはもっと知られるべきであろう。
日本でもそうであったように、学生運動の一部が過激化した。ドュチュケ自身が施設破壊活動を初期に肯定し、ゲバラらによるラテンアメリカでの武装闘争を礼賛していたことから後にその責任を問われるが、対人テロには終始反対していた。当局の諜報員が学生に火炎瓶や爆弾を配るなど過激化を誘導していたこと、また、ドュチュケ襲撃犯と極右組織との繋がりを当局が最近まで隠蔽していたことは重要な教訓である。私はかような事実を本書を通じて初めて知った。
68年4月、運動が高揚する中、東独出身の極右の青年に頬と頭と肩に銃弾を浴びせれ瀕死の重症を追い、一時期読み書きの能力を失うが、刑務所内で自殺しようとした襲撃犯、なお続く後遺症に苦しませた敵に、自殺しないよう説得したドュチュケの手紙は胸を打つ。
77年頃、直筆ノートに「民主主義なくして社会主義はない」と記したとされている(p221)が、これは1959年SPDゴーデスベルク綱領の有名な一節である。同時代に政権担当能力を有する国民政党へ着実に成長し、政権党として進歩的政策を実現つつあったSPDへの拒否感は少々理解に苦しむところであるが、1919年(当時つい半世紀前)のSPD政権による民主主義的社会主義者ローザ・ルクセンブルクやカール・リープクネリトらの殺害が尾を引いていたのかもしれない。
著者は民主主義的社会主義者ドュチュケが緑の党結成に動いた転換について、盛り上がり、連帯し、政界進出しつつあった環境保護団体の連合体を左派運動の拡大の場として利用しようとしたものではなく、「資本主義的産業発展がもたらしたエコロジー的危機は全人類を脅かす問題であり、この問題の解決なしには人間の解放をめざす社会主義の目標も達成できない、という考えであった」としている。最近、関心を集めている斎藤幸平らの脱成長社会主義もこの系譜に位置づけられよう。SPDの左側に上意下達的組織構造(民主集中制)をもつ社会主義新党を結成することは明確に否定していた(p246)。もし彼が生きていたら2007年の左翼党(Die Linken)の結成に際してはどう動いただろうか。左翼党は彼が否定していた民主集中制を当初から採用せず、派閥を認め、大胆な環境政策も掲げ、今なお多くの若者から支持を得ている。左翼党は緑の党以上にドュチュケの思想を体現している。入党すべきかどうか大いに迷ったのではないだろうか。
彼を真の社会主義革命を夢見て挫折し迷走した理想主義者として描くべきではなく、彼の生き様はジェンダー問題への向き合い方も含め反権威主義で一貫していた、と本書の最後に著者は述べている。まさにその通りだろう。
著者は「あとがき」で、ドイツと対比した日本の現状を憂いているが、全く同感である。SEALDsやグレタ・トゥーンベリのような、現状に異議を申し立て、よりよい世界を望む若者たちに、その望みは叶わない、現実はもっと複雑で変えられない、変えてはならない、黙って学んで働けと執拗に諭し、あまつさえ冷笑する中高年がいかに多いことか。脱権威主義化の進んだドイツでさえ90年を経て極右が再び伸長している。世界中で、なかんずく日本で、ルディのような魂の持ち主をいかに育てるか、われわれの世代に課せられた重い宿題である。



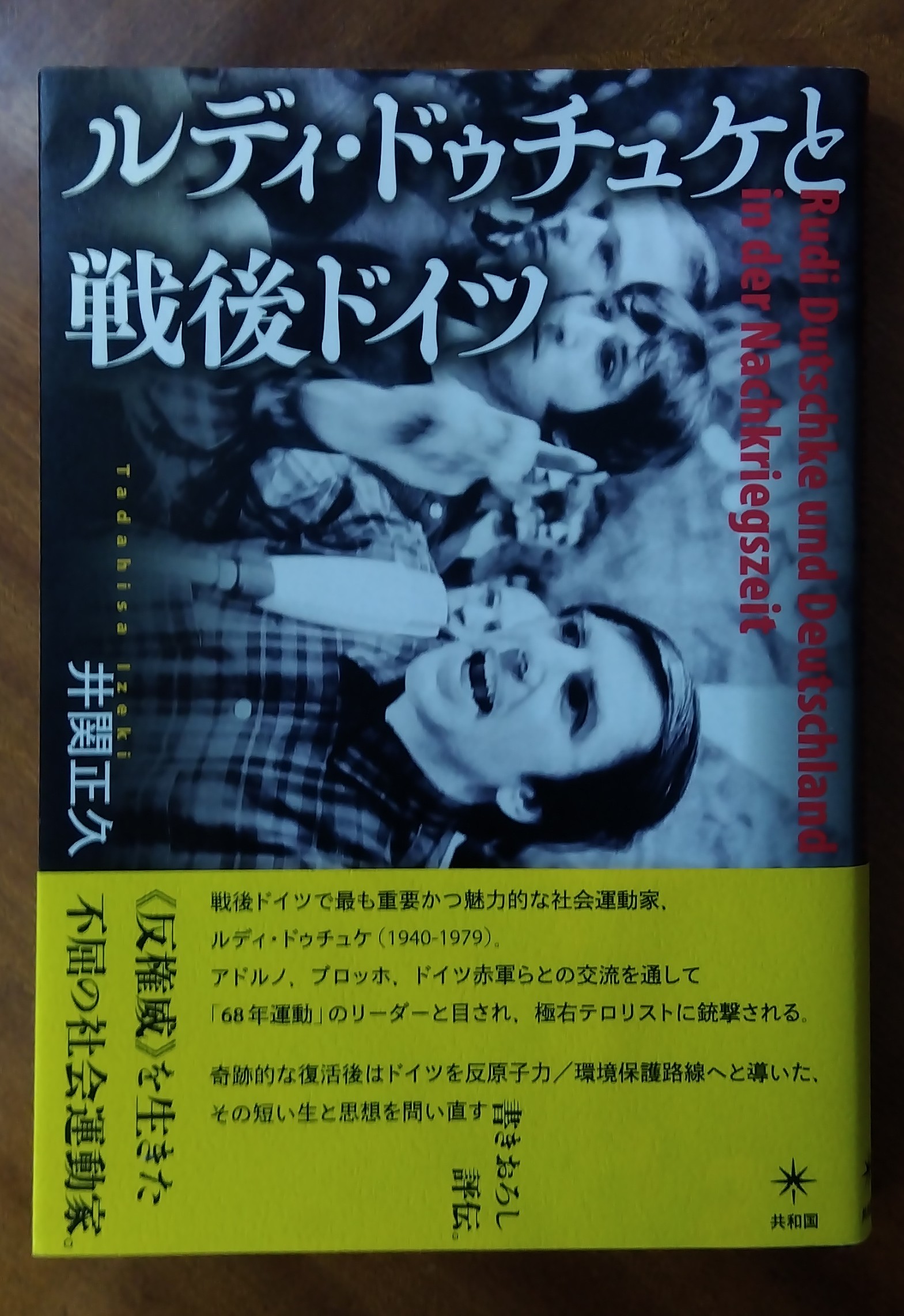 ルディ・ドュチュケは1940年東ドイツ生まれで軍入隊を拒否して西ドイツに逃れ、そこで学生運動のリーダーとなり、運動が頂点に達した1968年に極右青年の銃弾を受け瀕死の重症を負うものの、再びオピニオンリーダーとして「議会外反対運動」を推し進め、"ジーンズにセーターの議員団"緑の党(Die Grürnen)の結成の立役者の一人となり、結党直前の1979年に後遺症で死去した左派活動家である。東独の偽りだらけの「社会主義」体制もソ連によるチェコスロバキア侵略もドイツ赤軍によるテロも強く批判した民主主義的社会主義者であった。本書は一人の魅力的な人物の短くも波乱万丈の生涯を軸に戦後ドイツの政治史をたどるもので、ドュチュケ自身が運動の個人化に困惑し神格化に批判的であったことを踏まえつつ、平板な通史解説より惹き込まれる秀逸な手法で戦後ドイツの政治状況を伝えている。
ルディ・ドュチュケは1940年東ドイツ生まれで軍入隊を拒否して西ドイツに逃れ、そこで学生運動のリーダーとなり、運動が頂点に達した1968年に極右青年の銃弾を受け瀕死の重症を負うものの、再びオピニオンリーダーとして「議会外反対運動」を推し進め、"ジーンズにセーターの議員団"緑の党(Die Grürnen)の結成の立役者の一人となり、結党直前の1979年に後遺症で死去した左派活動家である。東独の偽りだらけの「社会主義」体制もソ連によるチェコスロバキア侵略もドイツ赤軍によるテロも強く批判した民主主義的社会主義者であった。本書は一人の魅力的な人物の短くも波乱万丈の生涯を軸に戦後ドイツの政治史をたどるもので、ドュチュケ自身が運動の個人化に困惑し神格化に批判的であったことを踏まえつつ、平板な通史解説より惹き込まれる秀逸な手法で戦後ドイツの政治状況を伝えている。