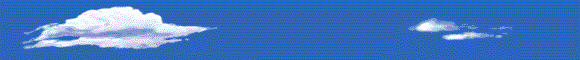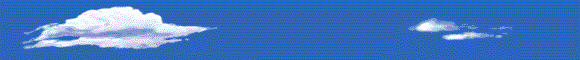[an error occurred while processing this directive]
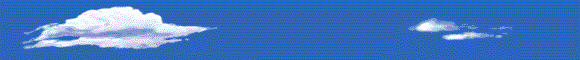
時速20km社会へ
2008年4月5日 藤巻晴行
 |
| '08年3月 アムステルダムで |
 |
自転車専用道があるので
安心して二人乗り三人乗りできる |
 |
| 様々なタイプの荷台付き自転車が普及している。 |
風力発電における風速3乗則をご存じだろうか。発電量は風速の3乗に比例するため、風が少しでも強い所の選定がきわめて重要であることを意味している。同じ法則は陸上交通における省エネルギーの物理的障壁の一つである空気抵抗にもあてはまる。空気抵抗は風速(移動速度)の二乗に概ね比例するという。仕事(エネルギー消費量)は力(摩擦抵抗)×距離である。従って早く移動するほど同じ距離を移動するのに必要なエネルギーは格段に大きくなる。現在の自動車の燃費が、平均時速80kmくらいで最高になるのは、あくまで内燃機関の特性(歩く早さでもエンジンの高速回転を維持しなければならないため)である。電気自動車にはそのような制約はない。
つまり、自動車交通の低速化は低炭素社会の必要条件である。
自動車の利便性の本質はその早さではなく、雨風をしのぎながら、幼児やお年寄り、病人など自転車での移動が困難な人を同乗させて目的地に着けることである(速度が本質ならばオートバイでもいいはず)。将来的には、一般道の制限速度を20kmとし、軽快自転車程度の低速移動に最適化した電気自動車(もしくは電動アシストベロタクシーを若干改良し、側面ドアを設けた電動アシスト3輪自転車)を主体とする自動車交通に移行すべきである。高速で移動したい場合には引き続き高速輸送を維持できる鉄道を利用すればよい。
低速化には省エネルギー以外にも様々なメリットがある。
まず、安全である。人間の反射神経はそもそも走る早さ以上の移動速度に適応していない。今後急増する高齢ドライバーにも適している。さらに、将来の主たる私的交通手段となる自転車を狭い道路で大きな速度差で追い越すことがなくなる。それゆえ事故件数を大幅に低下させるであろう。また、衝突の衝撃も速度の二乗に比例するから、事故が起きた場合の死傷率も大幅に下がるはずである。そのためボディをプラスチックやアルミニウムなどで軽量化することができる。騒音も、大気汚染物質の排出もほぼゼロとなる。
時速20kmは現在の都市近郊の平均走行速度と比べれば半分以下であるが、さりとてなお歩行速度の5倍であり、それほど利便性を損なうわけではない。渋滞の多い市街地の平均走行速度は現状でもその程度であろう。
低速自動車交通は個人の努力では実現できない。社会的合意に基づく制限速度の段階的引き下げが不可欠である。多くの方に賛同を呼びかけたい。