[an error occurred while processing this directive]
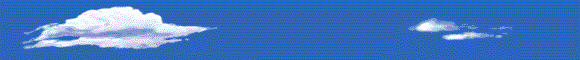
書評:戦後ドイツの抗議運動ー「成熟した市民社会」への模索
井関正久著, 岩波書店, 2016年6月発行
 「世界で良い影響を与えている国」の国際アンケートで首位の国。工業大国でありながら脱原発に舵を切り、再生可能エネルギーを積極的に導入し、移民や難民を寛大に受け入れ、高い福祉水準を維持しているにもかかわらず、財政規律を守り、高い成長率と国際競争力を維持するヨーロッパのリーダー。ドイツ連邦共和国は世界中の多くの人々にとって尊敬と羨望の対象である。私自身も、世界で唯一ドイツが有する労使共同決定法は経済活動の場でも民主主義を貫こうとする試みであり、人類の歴史を豊かで民主的で公正で持続可能な社会に向けた歩みと観るならば、ドイツは最も進んだ国と考えている。
「世界で良い影響を与えている国」の国際アンケートで首位の国。工業大国でありながら脱原発に舵を切り、再生可能エネルギーを積極的に導入し、移民や難民を寛大に受け入れ、高い福祉水準を維持しているにもかかわらず、財政規律を守り、高い成長率と国際競争力を維持するヨーロッパのリーダー。ドイツ連邦共和国は世界中の多くの人々にとって尊敬と羨望の対象である。私自身も、世界で唯一ドイツが有する労使共同決定法は経済活動の場でも民主主義を貫こうとする試みであり、人類の歴史を豊かで民主的で公正で持続可能な社会に向けた歩みと観るならば、ドイツは最も進んだ国と考えている。
戦争の廃墟からこのような国がいかに形づくられてきたか、本書は市民や学生による抗議運動の歴史からドイツ戦後史を学び考える本である。
抗議運動は実のところ挫折の連続であった。戦後の大規模な抗議運動は50年代初頭の再軍備反対運動により幕開けするが、それでも再軍備は進められた。68年をピークとする学生運動も非常事態法の通過を止めることはできなかった。80年代には過去の反省から「一点集中型」に成長したことが中距離核ミサイル配備の撤回などの実現につながり、さらに90年代には対決型から対話型、政策提言型に成長した経緯が詳しく述べられている。一方、環境保護運動の成熟は、やがて緑の党の結党と議会進出そして政権参加、既成政党による環境政策の積極的公約化という世界史上初の情勢を切り拓くことになる。
東ドイツの市民運動や体制批判運動について多くの紙面が割かれているのも本書の特徴である。ハンガリー動乱やプラハの春の前に「6月17日事件」と呼ばれる大規模な民主革命未遂事件が起こったことはあまり知られていないだろう。福音教会が市民運動や反体制運動の拠点となったことや、東ドイツ政府による文化的思想的統制を切り崩したサブカルチャーの役割も詳述されている。
また、極右や排外主義者による「抗議運動」の歴史と現状についても一章が割かれている。彼らがどのような状況でどのような手段を用いた時に盛り上がりを見せたのか。侵略と加害の歴史を共有し、ヘイトデモや神道政治連盟、日本会議など極右勢力による草の根的活動が活発化しているわが国の現状を憂う人にとっても参考になろう。
日本に生まれたばかりの「抗議文化」をいかに定着させ、政治家や官僚任せにしない参加民主主義を深めるか、本書は多くの示唆を与えてくれる。



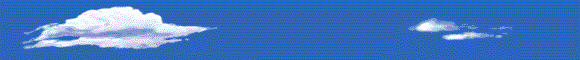
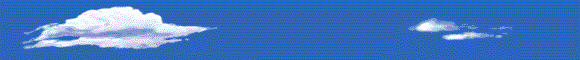
 「世界で良い影響を与えている国」の国際アンケートで首位の国。工業大国でありながら脱原発に舵を切り、再生可能エネルギーを積極的に導入し、移民や難民を寛大に受け入れ、高い福祉水準を維持しているにもかかわらず、財政規律を守り、高い成長率と国際競争力を維持するヨーロッパのリーダー。ドイツ連邦共和国は世界中の多くの人々にとって尊敬と羨望の対象である。私自身も、世界で唯一ドイツが有する労使共同決定法は経済活動の場でも民主主義を貫こうとする試みであり、人類の歴史を豊かで民主的で公正で持続可能な社会に向けた歩みと観るならば、ドイツは最も進んだ国と考えている。
「世界で良い影響を与えている国」の国際アンケートで首位の国。工業大国でありながら脱原発に舵を切り、再生可能エネルギーを積極的に導入し、移民や難民を寛大に受け入れ、高い福祉水準を維持しているにもかかわらず、財政規律を守り、高い成長率と国際競争力を維持するヨーロッパのリーダー。ドイツ連邦共和国は世界中の多くの人々にとって尊敬と羨望の対象である。私自身も、世界で唯一ドイツが有する労使共同決定法は経済活動の場でも民主主義を貫こうとする試みであり、人類の歴史を豊かで民主的で公正で持続可能な社会に向けた歩みと観るならば、ドイツは最も進んだ国と考えている。